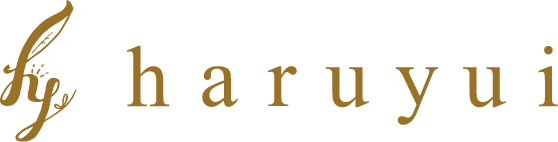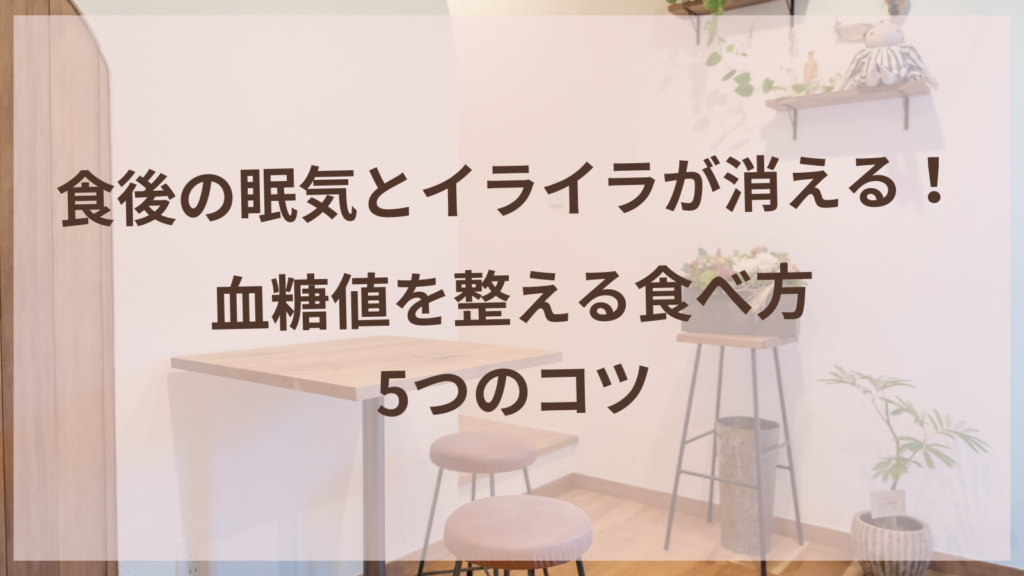こんにちは!はりきゅうサロンharuyui 鍼灸師・薬剤師の井土利恵です。
ランチの後、眠くて仕事に集中できない…。甘いものが無性に食べたくなる…。そんな経験、ありませんか?
実はそれ、血糖値の急激な変動が原因かもしれません。
食後の眠気やイライラは、誰にでも起こりうる体のサインなんです。でも、食べ方をちょっと工夫するだけで、驚くほど体調が変わることがあります✨
この記事を読むとわかること:
- 血糖値が乱れる仕組みと体への影響
- 血糖値を整える具体的な食べ方5つのコツ
- 東洋医学から見た消化機能のサポート方法
- 日常生活ですぐ実践できる具体的な工夫
こんな方におすすめ:
- 食後の眠気に悩んでいる40代50代女性
- 甘いものへの欲求が止まらない方
- 疲れやすさやイライラを感じている方
- ダイエットを成功させたい方
東洋医学では、秋は「脾(消化機能)」が弱りやすい季節です。食べ方を整えることは、体全体のバランスを整えることにつながるんです。
それでは、今日から実践できる血糖値を整える食べ方のコツを、一緒に見ていきましょう!
女性の美容や体の悩みでお困りの方へ
美容や体の変化でお悩みではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、女性らしい美しさを引き出すお手伝いをさせていただいています。
もし美容鍼や東洋医学に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
美容鍼について詳しくはこちら
食後の眠気とイライラの正体とは?
食後の不快な症状、実は体からの大切なメッセージなんです。まずは、その仕組みを理解していきましょう。
血糖値スパイクが引き起こす体の変化
血糖値スパイクという言葉、聞いたことありますか?これは、食後に血糖値が急激に上がって、その後急降下する現象のことです。
食事で糖質を摂ると、体内では血糖値が上がります。すると、すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されるんです。
このインスリンが血糖値を下げてくれるのですが、急激に上がった血糖値に対しては、インスリンも大量に出てしまいます😣
その結果、血糖値が急降下。この時に現れるのが、以下のような症状です:
- 強い眠気
- イライラ感
- 集中力の低下
- 無性に甘いものが食べたくなる
- 疲労感やだるさ
一般的に、この血糖値の乱高下が続くと、体への負担が大きくなると言われています。個人差はありますが、長期的には体重増加や代謝の低下にもつながる可能性があります。
東洋医学から見た「脾の乱れ」
東洋医学では、この状態を「脾(消化機能)の乱れ」として捉えます。
「脾」は、飲食物から「気(エネルギー)」や「血(栄養)」を作り出す大切な臓器です。西洋医学でいう脾臓とは少し違って、消化吸収全体の働きを指しているんです。
脾の働きが弱ると、こんな症状が出やすくなると言われています:
- 疲れやすい
- 食後に眠くなる
- むくみやすい
- お腹が張りやすい
- 軟便や下痢気味
これを「脾気虚(ひききょ)」と呼びます。食べたものを上手にエネルギーに変えられない状態なんです。
個人の体質により体験には個人差がありますが、東洋医学的なアプローチで脾の働きをサポートすることが期待されています。
体質を全体から捉えた血糖値の乱れの原因
血糖値が乱れる原因は、食べ物だけではありません。現代の生活習慣や季節の影響も深く関わっているんです。
現代の食生活と血糖値の関係
現代の食生活には、血糖値を乱しやすい要因がたくさんあります。
精製された糖質の多さ
白米、白いパン、麺類、お菓子など、精製された糖質は消化吸収が早く、血糖値を急上昇させやすいんです。
早食いの習慣
忙しい毎日の中で、つい早食いになっていませんか?早食いは血糖値スパイクの大きな原因です。
食事の時間が不規則
朝食を抜いたり、夜遅くに食事をしたりすると、体内リズムが乱れて血糖値のコントロールが難しくなります。
ストレス
ストレスホルモンは血糖値を上げる働きがあると言われています。慢性的なストレスは要注意です。
秋の季節と消化機能の関わり
東洋医学では、季節と体の関係をとても大切に考えます。
秋は「肺」と「脾」のケアが重要な季節とされているんです。
秋の特徴は「燥邪(そうじゃ)」。つまり、乾燥です。この乾燥が、肺だけでなく消化機能にも影響を与えると考えられています。
脾は湿度を好む臓器なので、乾燥する秋は脾の働きが弱りやすくなるんです。そのため、秋は特に消化に優しい食べ方を心がけることが大切です🍂
気・血・水のバランスから見る血糖値
東洋医学では、体を「気・血・水」という3つの要素で考えます。
気(き):エネルギー
「気虚」の状態だと、脾の働きが弱く、食べたものをエネルギーに変える力が不足します。
血(けつ):栄養
「血虚」の状態だと、栄養が全身に行き渡らず、疲れやすくなります。
水(すい):体液
「痰湿(たんしつ)」といって、余分な水分や老廃物が溜まると、代謝が悪くなり、むくみやすくなります。
血糖値の乱れは、この3つのバランスが崩れているサインかもしれません。個人差がありますが、東洋医学的なケアでバランスを整えることが期待されています。
血糖値を整える食べ方5つのコツ
それでは、今日から実践できる具体的な方法をご紹介します!どれも簡単なので、できることから始めてみてくださいね✨
コツ1:野菜・海藻類から食べ始める
食事は「野菜ファースト」が基本です!
野菜や海藻に含まれる食物繊維が、後から入ってくる糖質の吸収を緩やかにしてくれるんです。
おすすめの野菜:
- 葉物野菜(ほうれん草、小松菜、レタス)
- きのこ類(しめじ、えのき、しいたけ)
- 海藻(わかめ、もずく、ひじき)
- ブロッコリー、キャベツ
食べ方のポイント:
- 量の目安は両手いっぱい程度
- 最初の5分間は野菜だけを食べる
- よく噛んで、ゆっくりと
サラダ、お浸し、酢の物など、調理法は何でもOKです。温野菜なら、秋の冷えた体も温まって一石二鳥ですよ🥗
コツ2:次にタンパク質(肉・魚・大豆製品)
野菜の次は、タンパク質を食べましょう。
タンパク質は消化に時間がかかるため、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。また、満足感も高まるので、食べ過ぎ防止にもつながるんです。
おすすめの食材:
- 魚(特に青魚は良質な油も摂れます)
- 鶏肉(皮を除けば低脂肪)
- 豆腐、納豆などの大豆製品
- 卵
量の目安:
1食あたり、手のひらサイズ(厚さも含めて)が目安です。
一般的に、タンパク質をしっかり摂ることで、筋肉量の維持や代謝のサポートにもつながると言われています。個人差はありますが、40代50代の女性には特に意識していただきたいポイントです。
コツ3:炭水化物は最後に
ご飯やパン、麺類などの炭水化物は、最後に食べるのがおすすめです。
野菜とタンパク質を先に食べることで、すでにお腹がある程度満たされています。その状態で炭水化物を食べると、自然と量を減らせるんです。
炭水化物を食べるときのポイント:
- 量の目安はお茶碗軽く1杯(150g程度)
- 玄米や雑穀米にすると食物繊維も摂れる
- よく噛んで食べる
- 完食しなくても大丈夫
「炭水化物を食べてはいけない」わけではありません。食べる順番と量を工夫することで、血糖値を整えながら美味しくいただけます🍚
詳しい食事の順番と組み合わせについては、こちらの記事もご覧ください。
コツ4:よく噛んでゆっくり食べる(一口30回)
早食いは血糖値スパイクの大きな原因です。よく噛むことで、たくさんのメリットがあるんです!
よく噛むメリット:
- 満腹中枢が刺激されて、少量でも満足できる
- 消化がスムーズになる
- 食べ物の味をしっかり感じられる
- 顔の筋肉を使うので、小顔効果も期待できる
実践のコツ:
- 一口30回を目標に
- 食事時間は最低でも15~20分かける
- 一口食べたら箸を置く習慣をつける
- 誰かと会話しながら食べる
最初は意識しないと難しいかもしれませんが、慣れてくると自然にできるようになりますよ✨
コツ5:間食には低GI食品を選ぶ
どうしても間食したい時は、GI値の低い食品を選びましょう。
GI値とは、食後の血糖値の上がりやすさを示す指標です。GI値が低いほど、血糖値の上昇が緩やかになります。
おすすめの間食:
- ナッツ類(アーモンド、くるみ、カシューナッツ)
- チーズ
- 無糖ヨーグルト
- 果物(りんご、みかん、キウイなど)
- ゆで卵
避けたい間食:
- 菓子パン
- 清涼飲料水
- スナック菓子
- チョコレート菓子
甘いものが欲しい時は、果物にヨーグルトを添えるのがおすすめです。果物の自然な甘みで満足感が得られますよ🍎
実践!シーン別の食べ方の工夫
理論は分かったけど、実際の生活でどう実践すればいいの?そんな疑問にお応えします!
外食時の選び方
外食でも、血糖値を整える食べ方はできるんです。
おすすめの選び方:
- 定食を選ぶ(小鉢が多いと野菜が摂りやすい)
- サラダや小鉢から食べ始める
- 丼ものよりも定食スタイル
- 麺類の場合は、野菜たっぷりのものを
実践例:
- 和定食:小鉢(煮物や酢の物)→お味噌汁→焼き魚→ご飯
- 洋食:サラダ→スープ→メイン(肉や魚)→パン
- 中華:前菜→スープ→主菜→ご飯や麺
ファストフードの場合は、サラダをプラスするだけでも違いますよ!
お弁当の詰め方と食べ方
お弁当を作る方も、買う方も使えるコツです。
お弁当を作る場合:
- 野菜のおかずを取り出しやすい位置に
- 彩りよく詰めると、自然と野菜が増える
- ミニトマトやブロッコリーを仕切りに使う
コンビニ弁当を選ぶ場合:
- 野菜がたっぷり入っているものを選ぶ
- サラダを別に買う
- お弁当だけでなく、温かいスープも一緒に
食べる順番:
野菜のおかず→タンパク質のおかず→ご飯の順で食べましょう。
お弁当箱を開けた時に、どこから食べるか決めておくとスムーズですよ🍱
家族との食事での実践法
家族と一緒に食べる時こそ、良い習慣を共有するチャンスです。
大皿料理の工夫:
- 野菜料理を最初に取り分ける
- サラダボウルを食卓の中央に
- お味噌汁やスープを先に飲む
食卓の配置:
- 野菜料理を手前に置く
- ご飯は少し離れた位置に
- おかわりは立って取りに行く(自然と食べ過ぎ防止に)
家族みんなで実践:
家族で「野菜から食べようね」と声を掛け合うと、習慣づきやすいです。お子さんの食育にもつながりますよ😊
内臓脂肪が気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。
東洋医学でサポートする血糖値バランス
食べ方の工夫に加えて、東洋医学的なアプローチも取り入れてみませんか?
脾の働きを助けるツボ
東洋医学では、ツボ刺激で脾の働きをサポートすると考えられています。自宅で簡単にできるセルフケアをご紹介しますね。
足三里(あしさんり)
- 場所:膝のお皿の外側から、指4本分下
- 効果:消化機能をサポートすると伝統的に言われている
- 押し方:親指でゆっくり3秒押して、3秒離す。これを5回繰り返す
三陰交(さんいんこう)
- 場所:内くるぶしから指4本分上
- 効果:脾・肝・腎の経絡が交わる重要なツボ
- 押し方:優しく円を描くようにマッサージ
中脘(ちゅうかん)
- 場所:おへそとみぞおちの中間
- 効果:胃の調子を整えると伝統的に考えられている
- 押し方:手のひら全体で、時計回りに優しくさする
※個人の体質により体験には個人差があります。効果を保証するものではありません。
耳ツボで食欲をコントロール
耳には、全身のツボが集まっていると言われています。特に食欲に関連するツボを刺激することで、食べ過ぎのサポートが期待できます。
神門(しんもん)
- 場所:耳の上部の三角の窪み
- 効果:リラックスをサポートすると言われている
胃点(いてん)
- 場所:耳の中央あたり
- 効果:消化機能に関連すると考えられている
内分泌点(ないぶんぴつてん)
- 場所:耳の穴の下部
- 効果:ホルモンバランスに関連すると言われている
刺激方法:
綿棒や指の腹で、優しく円を描くように5秒ずつ押しましょう。食前に行うのがおすすめです。
食欲のコントロールについて、夜の食欲コントロールや耳ツボ刺激の記事も参考にしてください。
鍼灸でのケアアプローチ
セルフケアも大切ですが、プロの施術を受けることで、より深いケアが可能になります。
haruyuiでは、お一人おひとりの体質に合わせた耳ツボダイエットプログラムをご提供しています。
当サロンの特徴:
- 鍼灸師・薬剤師による専門的なカウンセリング
- 体質診断に基づいた個別プラン
- 食事指導と耳ツボ施術の組み合わせ
- 女性専用の落ち着いた空間
耳ツボダイエットでは、食欲のコントロールをサポートしながら、体質改善を目指していきます。無理な食事制限ではなく、体の内側から整えるアプローチです。
食後の眠気やイライラでお困りの方、ダイエットがなかなか続かない方は、ぜひご相談ください。食後の眠気解消についての記事もご覧ください。
※個人の体質により体験には個人差があります。効果を保証するものではありません。医療行為の代替ではありません。
まとめ:血糖値を整えて快適な毎日を
ここまで、血糖値を整える食べ方5つのコツをお伝えしてきました。もう一度おさらいしましょう✨
5つのコツ:
- 野菜・海藻類から食べ始める
- 次にタンパク質(肉・魚・大豆製品)
- 炭水化物は最後に
- よく噛んでゆっくり食べる(一口30回)
- 間食には低GI食品を選ぶ
全部を一度に実践するのは大変かもしれません。まずは1つから、できることから始めてみてください。
今日からできる簡単なステップ:
- 今日の夕食は、野菜から食べてみる
- 一口30回を意識してみる
- 間食にナッツを用意しておく
小さな習慣の積み重ねが、大きな変化につながります。3週間続けると、体の変化を実感できるかもしれません。
食後の眠気やイライラから解放されて、午後も元気に過ごせる毎日。甘いものへの欲求に振り回されない自分。そんな快適な毎日を、一緒に目指していきましょう!
一人で続けるのが難しい時は、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。体質に合わせたアドバイスを受けることで、より効果的にケアを進められますよ。
栄養や食事について、厚生労働省の栄養・食育対策のページも参考にしてください。
あなたの体は、毎日の食事で作られています。今日からの食べ方で、未来の体が変わります。
応援しています!💪✨
専門家と一緒に美容ケアを始めませんか?
美容は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。はりきゅうサロンharuyuiで、あなたの体質に合わせた美容プランを一緒に考えていきましょう。