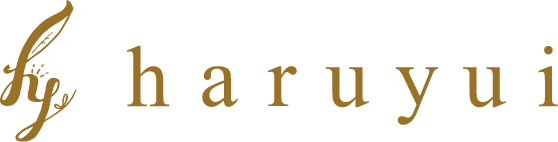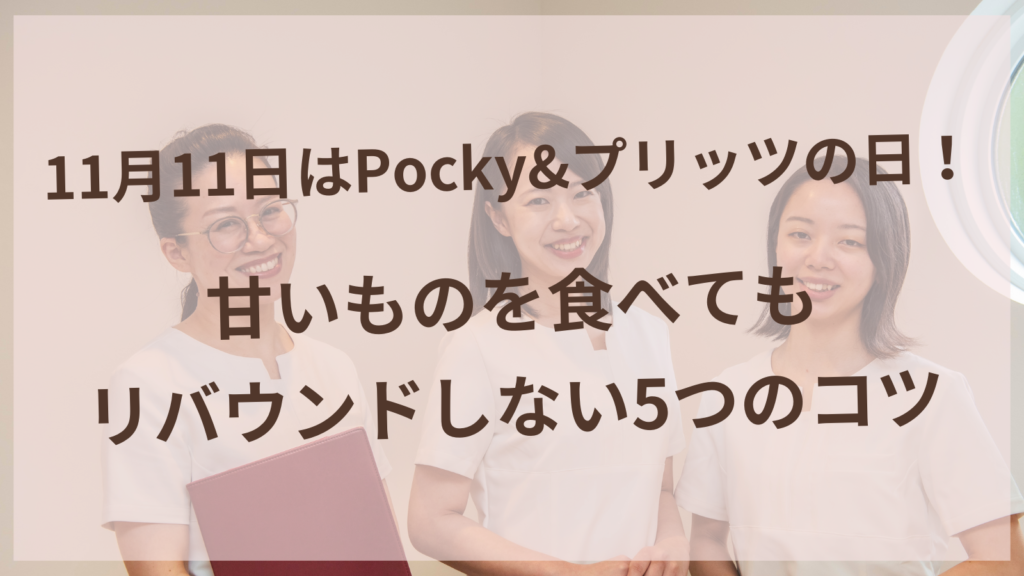こんにちは!はりきゅうサロンharuyui 鍼灸師・薬剤師の井土利恵です。
11月11日はPocky&プリッツの日ですね!この日は、職場や家族と甘いものを楽しむ方も多いかもしれませんね。
でも、「食べたいけど太りたくない」「せっかくダイエットしてるのに…」と罪悪感を感じていませんか?
実は、甘いものを食べることそのものが問題なのではなく、食べ方や食べた後のケアが、リバウンドするかどうかの分かれ道なんです✨
40代50代の体は、若い頃とは違った反応を示します。だからこそ、体質に合った「上手な付き合い方」を知っておくことが大切なんですね。
女性の美容や体の悩みでお困りの方へ
美容や体の変化でお悩みではありませんか?当院では、東洋医学の観点から体質改善をサポートし、女性らしい美しさを引き出すお手伝いをさせていただいています。
もし美容鍼や東洋医学に興味がおありでしたら、お気軽にご相談ください。
美容鍼について詳しくはこちら
このブログを読むとわかること:
- なぜ甘いものを食べるとリバウンドしやすいのか
- 甘いものを食べてもリバウンドしない5つのコツ
- 東洋医学の視点から見た「甘味」と体の関係
- 食欲をコントロールするための体質改善法
こんな方におすすめの記事です:
- Pocky&プリッツの日を罪悪感なく楽しみたい方
- ダイエット中でも甘いものを我慢したくない方
- リバウンドを繰り返している40代50代女性
- 食欲コントロールに悩んでいる方
今日は、東洋医学と栄養学の視点から、甘いものとの上手な付き合い方をお伝えしていきますね!
なぜ甘いものを食べるとリバウンドしやすいの?
「ちょっとだけ…」のつもりが止まらなくなった経験、ありませんか?
実は、甘いものがリバウンドを招くのには、ちゃんとした理由があるんです。体の仕組みと東洋医学の視点から、その理由を見ていきましょう。
血糖値の乱高下が食欲を暴走させる
空腹時に甘いものを食べると、血糖値が急上昇します。すると体は、血糖値を下げるためにインスリンを大量に分泌するんですね。
その結果、今度は血糖値が急降下してしまいます💦
血糖値が下がると、脳が「エネルギー不足だ!」と判断し、さらに甘いものを欲してしまうんです。これが「一度食べると止まらない」状態を作り出します。
一般的に、血糖値の乱高下は体への負担となると言われています。個人差がありますが、安定した血糖値を保つことが食欲コントロールのサポートにつながると考えられているんですね。
40代以降は代謝が落ちて脂肪になりやすい
加齢により基礎代謝が低下するのは、筋肉量の減少やホルモンの変化が関係しています。
若い頃と同じ量を食べても、消費されにくくなっているんです。特に糖質は、消費されないと脂肪として蓄積されやすいと言われています。
40代以降の女性は、エストロゲンの減少により内臓脂肪がつきやすくなる傾向があります。個人の体質により差はありますが、年齢に応じた食べ方の工夫が大切なんですね。
東洋医学で考える「甘味」と「湿」の関係
東洋医学では、甘味は「脾(消化器系)」を養う働きがあるとされています。適度な甘味は体に必要なものなんです✨
しかし過剰摂取は「湿邪(しつじゃ)」を生み出すと考えられています。「湿」が体内に溜まると、むくみ、だるさ、代謝低下を招く可能性があるんですね。
特に秋は「肺」と「脾」が影響を受けやすい季節とされています。甘いものの食べ過ぎで「湿」が増えると、体の巡りが悪くなり、さらに代謝が落ちるという悪循環に陥ることがあります。
体質を全体からとらえた「甘いもの欲求」の原因
「また食べてしまった…私って意志が弱いのかな」そんなふうに自分を責めていませんか?
でも実は、甘いものを欲するのは、単なる「意志の弱さ」ではないんです。体からの大切なサインなんですよ。
ストレスと「気の滞り」
ストレスを感じると、幸せホルモン「セロトニン」が不足しがちになります。
脳は手っ取り早くセロトニンを増やすため、甘いものを欲する傾向があるんです。これは体の自然な反応なんですね。
東洋医学では、ストレスは「肝」の働きを乱し、「気」の巡りを滞らせると考えられています。「気滞(きたい)」の状態では、イライラや不安感とともに甘いものへの欲求が高まることがあります。
ストレスケアと気の巡りを整えることが、根本的な食欲コントロールのサポートにつながると言われているんですよ。
睡眠不足とホルモンバランスの乱れ
睡眠不足は、食欲を増進するホルモン「グレリン」を増やし、満腹感を与えるホルモン「レプチン」を減らすと言われています。
結果として、特に高カロリーで甘いものを欲しやすくなる傾向があるんです。
東洋医学では、睡眠は「血」を養う大切な時間とされています。「血虚(けっきょ)」の状態では、体が栄養を求めて甘味を欲することがあるんですね。
質の良い睡眠を確保することが、健康的な食欲のサポートにつながります✨
「脾」の働きが弱っているサイン
東洋医学で「脾」は消化吸収を司る臓器とされています。脾の働きが弱ると(脾虚:ひきょ)、以下のような症状が現れることがあります:
- 疲れやすい、だるい
- むくみやすい
- 甘いものを異常に欲する
- 食後の眠気
脾虚の状態では、甘味で一時的にエネルギーを補おうとする傾向があります。しかし根本的には、脾の働きをサポートする生活習慣が必要なんですね。
詳しくは食後の眠気をスッキリ解消!東洋医学の消化力アップ術もご覧ください。
甘いものを食べてもリバウンドしない5つのコツ
それでは、お待たせしました!甘いものを楽しみながらもリバウンドを防ぐ、5つの具体的なコツをお伝えしていきますね😊
コツ1:食べる「タイミング」で体への影響が変わる
避けるべきタイミングは、空腹時や食事前です。これは血糖値の急上昇を招いてしまいます。
おすすめのタイミングは:
- 食後30分~1時間後(血糖値が安定している時)
- 午後2時~4時(東洋医学で脾の働きが活発な時間帯とされています)
食後のデザートは、食事で血糖値が上がった後なので急激な変動を避けられます。このタイミングで適量を楽しむことで、体への負担を軽減できると言われているんですよ。
個人差はありますが、タイミングを意識するだけで食後の満足感や体調に違いを感じる方もいます✨
コツ2:「組み合わせ」で血糖値の急上昇を防ぐ
おすすめの組み合わせをご紹介しますね:
- ナッツやチーズなど、タンパク質・良質な脂質を一緒に
- 温かいお茶(プーアール茶、ほうじ茶など)
- 食物繊維を事前に摂る(野菜、海藻、きのこ類)
タンパク質や脂質は消化に時間がかかるため、血糖値の上昇が緩やかになると言われています。お茶のポリフェノールは、糖の吸収を穏やかにするサポートが期待されているんです。
これにより、血糖値の乱高下を防ぎ、その後の食欲をコントロールしやすくなる可能性があります。
代謝アップで痩せやすい体に!食事の順番と組み合わせも参考にしてみてくださいね。
コツ3:「量」よりも「質」を意識した選び方
量を減らして質を上げることを意識してみましょう:
- 本当に好きなもの、満足度の高いものを少量
- 質の良いチョコレート(カカオ70%以上)
- 添加物の少ない和菓子
五感で味わうことも大切です!
- 「ながら食べ」を避ける
- 見た目、香り、食感、味をゆっくり楽しむ
- 満足感を得ることで、その後の過食を防ぐサポートに
少量でも心から満足できれば、脳が「十分」と判断しやすくなると言われています。個人差はありますが、質を重視することで結果的に摂取量を抑えられる方も多いんですよ😊
コツ4:食べた後の「リセット習慣」を持つ
翌日の朝のリセット法をご紹介します:
- 白湯を飲んで体を温める
- 朝食は軽めに(お粥、野菜スープなど消化の良いもの)
- 果物や発酵食品で腸内環境をサポート
体を動かすことも効果的です:
- 軽い散歩やストレッチで代謝をサポート
- 20分程度の有酸素運動
耳ツボ刺激も手軽にできるケアです:
- 「神門(しんもん)」:耳の上部にあり、自律神経を整えるサポートが期待されるツボ
- 「飢点(きてん)」:耳の穴の前にあり、食欲調整のサポートが期待されるツボ
優しく押したり、綿棒で刺激することで手軽にケアできますよ。
罪悪感を持つのではなく、「楽しんだ後は整える」という前向きなマインドが大切なんです✨
夜の食べ過ぎで自己嫌悪!東洋医学で見つける根本的な解決法3選も参考にしてみてください。
コツ5:「甘いもの欲求」の本当の原因を知る
根本的な原因にアプローチすることが、長期的な成功の鍵です:
- 十分な睡眠(7時間以上が理想的と言われています)
- ストレスケア(深呼吸、瞑想、趣味の時間)
- 適度な運動(週3回程度のウォーキングなど)
- バランスの取れた食事(タンパク質、脂質、炭水化物をバランスよく)
体質改善のアプローチも大切です:
- 東洋医学的には、「気・血・水」のバランスを整えることが大切とされています
- 個人の体質に合わせたケアが必要です
- 耳ツボダイエットでは、体質そのものからサポートすることを目指します
一時的な我慢ではなく、自然と食欲がコントロールできる体質を目指すことが、リバウンドしないダイエットの鍵だと言われています。
食べないのに痩せない悩みを解決!代謝をサポートする食事の順番と組み合わせ5選や食後の眠気とイライラが消える!血糖値を整える食べ方5つのコツも合わせてご覧くださいね。
耳ツボダイエットで食欲コントロールをサポート
ここまで、甘いものとの上手な付き合い方をお伝えしてきました。でも、「一人で続けるのは難しい…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな方には、耳ツボダイエットという選択肢もあるんですよ😊
食欲調整に関わる耳ツボとは
耳には全身のツボが集まっていると東洋医学では考えられています。
主な耳ツボをご紹介しますね:
- 「神門」:自律神経を整えるサポートが期待されます
- 「飢点」:食欲調整のサポートが期待されます
- 「胃」「脾」:消化機能のサポートが期待されます
- 「内分泌」:ホルモンバランスを整えるサポートが期待されます
耳ツボを刺激することで、伝統的に食欲の調整や代謝のサポートに用いられてきました。個人差はありますが、継続的な刺激により体質改善のお手伝いができると考えられているんです。
夜の食欲コントロール!東洋医学の耳ツボダイエットで詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
体質改善で自然と食欲がコントロールできる状態へ
はりきゅうサロンharuyuiの耳ツボダイエットでは:
- 個々の体質に合わせた耳ツボを選定
- 無理な食事制限はせず、体質改善を重視
- 代謝アップのサポートを目指します
単に「我慢する」のではなく、「自然と適量で満足できる体」を目指すんですね✨
東洋医学の観点から、気・血・水のバランスを整えるお手伝いをします。継続的なサポートにより、リバウンドしにくい体質作りのお手伝いができると考えています。
※個人の体質により効果には個人差があります。
内臓脂肪を減らす正しい食べ方ガイドも参考にしてみてくださいね。
まとめ:甘いものは「敵」ではなく「上手に付き合うもの」
Pocky&プリッツの日も、罪悪感なく楽しめる5つのコツをお伝えしてきました。
5つのコツを振り返ると:
- 食べる「タイミング」を意識する(食後や午後2~4時)
- ナッツやお茶と「組み合わせる」
- 「量」より「質」を重視して五感で味わう
- 食べた後の「リセット習慣」を持つ
- 根本的な「甘いもの欲求の原因」にアプローチする
甘いものを完全に我慢する必要はないんです。大切なのは、タイミング、組み合わせ、そしてリセット習慣なんですね😊
そして何より、根本的な体質改善が重要です。睡眠、ストレスケア、適度な運動、バランスの取れた食事…これらが整うことで、自然と食欲がコントロールできる体になっていくんですよ。
一人で頑張るのが難しい場合は、プロのサポートを受けることも選択肢の一つです。東洋医学の視点から、あなたの体質に合わせたサポートができればと思います。
11月11日、Pocky&プリッツの日を楽しみながら、理想の体を目指していきましょう!✨
専門家と一緒に美容ケアを始めませんか?
haruyuiについて詳しくはこちら
美容は継続が大切です。一人で続けるのが難しい場合は、プロのサポートを受けることをお勧めします。はりきゅうサロンharuyuiで、あなたの体質に合わせた美容プランを一緒に考えていきましょう。