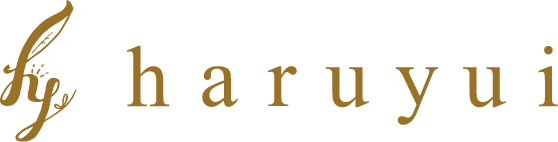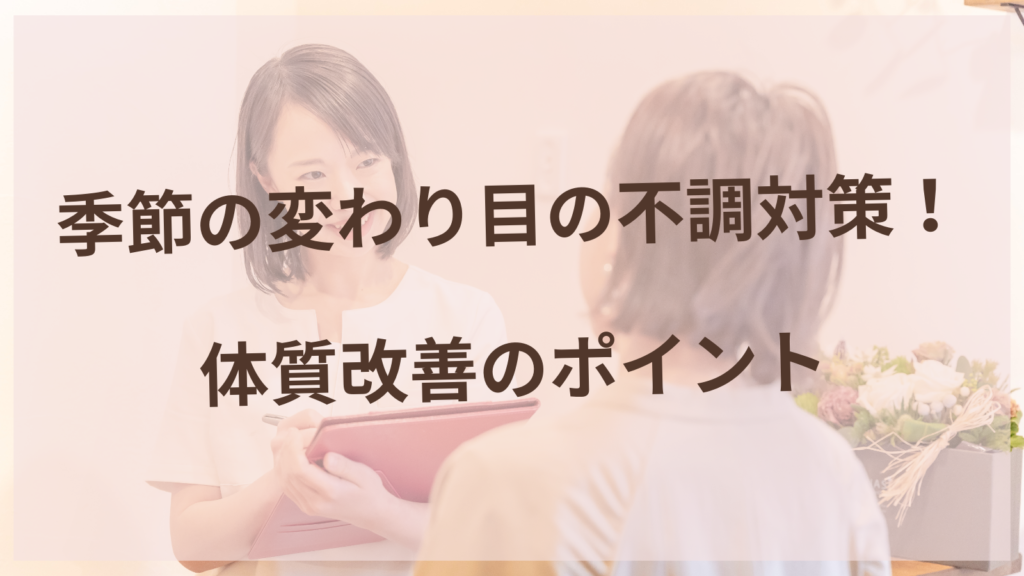
こんにちは!鍼灸師・薬剤師の井土利恵です。季節の変わり目、なんとなく体調が優れない…そんな経験ありませんか?実は「なんとなく」の不調には、東洋医学的な理由があるんです。
このブログでは、季節の変わり目に起こりやすい不調のメカニズムを東洋医学の視点から解説し、自宅でできる対策から専門的なケアまでご紹介します。季節に振り回されない、強い体質づくりのポイントを身につけていきましょう!
季節の変わり目に不調が起きる理由
「春はなんとなくだるい」「秋になると肌がカサカサする」…季節の変わり目になると、こうした不調を感じる方が多いのは偶然ではありません。
西洋医学から見た季節性の体調変化
西洋医学では、季節の変わり目の不調の原因として、主に以下の要因が考えられています:
- 気温や気圧の急激な変化による自律神経への負担
- 日照時間の変化によるホルモンバランスの乱れ
- 花粉やウイルスなど季節特有の外的要因の増加
これらの変化に体がうまく適応できないと、頭痛やめまい、倦怠感などさまざまな症状として現れるのです。
東洋医学から見た季節の変わり目の不調の原因
東洋医学では、季節の変化を「五行説」という独自の視点で捉えます。
五行説では、春は「木」、夏は「火」、土用(季節の変わり目)は「土」、秋は「金」、冬は「水」のエネルギーが高まる時期とされています。
このエネルギーの変化に体の「気」の流れがついていけないと、不調が現れると考えるのです。特に季節の変わり目にあたる「土用」の時期は、体の中心である「脾胃(ひい)」の働きが重要になります。
40代・50代女性に特に起こりやすい季節の変わり目症状
40代・50代の女性は、ホルモンバランスの変化も重なり、季節の変わり目の影響をより強く受けやすくなります!
- 自律神経の乱れによる不眠やホットフラッシュ
- 肌の乾燥や肌荒れの悪化
- むくみや冷えの増加
- 疲れやすさや気分の落ち込み
これらの症状は「仕方ない」と諦めるのではなく、適切なケアで改善できるものなんです。
東洋医学の「気・血・水」で考える体質改善
東洋医学では、体調を「気・血・水」という3つの要素のバランスで考えます。季節の変わり目の不調も、これらの乱れが原因と言えるでしょう。
「気」の巡りを良くして自律神経を整える方法
「気」とは生命エネルギーのことで、自律神経の働きに近い概念です。季節の変わり目は特に「気」が乱れやすい時期です。
「気」の巡りを良くするポイント:
- 深呼吸で肺の機能を高める(朝晩5分の腹式呼吸)
- 肩や首の凝りをほぐし「気」の流れを改善
- 規則正しい生活で「気」の消耗を防ぐ
特に効果的なのが、肺と大腸の「気」を整えるツボ「列缺(れっけつ)」の刺激です。手首のしわから親指側に約3cmのくぼみを、親指で優しく押してみましょう。
「血」の質を高めて免疫力アップする食習慣
「血」は栄養や酸素を運ぶ役割だけでなく、免疫力とも深く関わっています。
「血」を豊かにする食習慣:
- 良質なたんぱく質(豆腐、魚、鶏肉など)を毎食少しずつ
- 鉄分を含む食材(ひじき、レバー、小松菜など)を積極的に
- 根菜類(ごぼう、にんじん、れんこんなど)でエネルギーを蓄える
- 白砂糖や精製された炭水化物を控える
季節の変わり目には特に「脾」の働きを高める食べ方が効果的です。よく噛んで、温かいものを少量ずつ、規則正しく摂りましょう。
「水」の滞りを解消してむくみや冷えを防ぐコツ
「水」は体内の水分バランスを指し、リンパの流れにも関連しています。季節の変わり目にはむくみや冷えとして現れやすいのが特徴です。
「水」の滞りを解消するポイント:
- 朝一番の白湯で水分代謝を促進
- 塩分の取りすぎに注意
- 適度な運動でリンパの流れを活性化
- 腎経(じんけい)を温めるために腰や足元を冷やさない
むくみが気になる方におすすめなのが、足の「三陰交(さんいんこう)」というツボ。くるぶしの内側から指4本分上がったあたりを、親指で優しく押してみてください。
季節別・自宅でできるセルフケア術
季節ごとに起こりやすい不調は異なります。それぞれの季節の変わり目に合わせたケア法をご紹介します。
春→夏の変わり目に効果的なツボと生活習慣
春から夏への変わり目は、「木」から「火」へのエネルギー変化の時期。肝臓(東洋医学での「肝」)の機能を整えることが大切です。
春→夏のセルフケア:
- 早寝早起きのリズムを整える
- 緑の野菜や酸味のある食材を取り入れる
- イライラを溜めないよう、適度な運動で発散
この時期におすすめのツボは「太衝(たいしょう)」。足の親指と人差し指の骨が交わる部分にあります。イライラや頭痛の緩和に効果的です。
夏→秋の変わり目に整えたい食事と養生法
夏から秋への変わり目は、「火」から「土」を経て「金」へと変わる時期。胃腸(東洋医学での「脾胃」)の負担が大きくなりがちです。
夏→秋のセルフケア:
- 冷たい飲食物を控え、常温か温かいものを選ぶ
- 消化に優しい食事(おかゆ、スープなど)を増やす
- 腹部を冷やさないよう注意する
この時期に活性化したいのは「脾経(ひけい)」。足の内側を通る経絡で、特に「足三里(あしさんり)」というツボが効果的です。すねの外側、膝下約4本指下のくぼみを押してみましょう。
秋→冬、冬→春の変わり目に取り入れたい習慣
秋から冬、そして冬から春への変わり目は、「金」から「水」、「水」から「木」へのエネルギー移行期。呼吸器系と腎臓の機能を守ることが重要です。
秋→冬、冬→春のセルフケア:
- 乾燥対策として十分な保湿と水分摂取
- 腰や足先を温め、「腎」のエネルギーを守る
- 無理をせず十分な休息を取る
この時期に特に意識したいのが「腎経(じんけい)」。足の裏から内側を通り、胸に至る経絡です。特に「湧泉(ゆうせん)」という足裏の中央にあるツボは、朝晩刺激すると体を温める効果が期待できます。
専門家による季節の変わり目ケア
セルフケアに加えて、専門家による適切な施術を受けることで、季節の変わり目の不調をより効果的に改善できます。
鍼灸施術で得られる季節の変わり目対策の効果
鍼灸施術は、経絡上の特定のツボに働きかけることで、体全体のバランスを整えます。特に季節の変わり目には以下の効果が期待できます:
- 自律神経のバランス調整
- 血流改善による代謝アップ
- 免疫力の向上
- 疲労回復と深い休息の促進
一般的なマッサージとの大きな違いは、表面的な筋肉のほぐしだけでなく、内臓機能の調整や体質改善にアプローチできる点です。
あなたの体質に合わせた施術プランの重要性
東洋医学では、同じ症状でも原因は人それぞれ異なると考えます。例えば、同じ「疲れやすさ」でも:
- 「気」が不足している方
- 「血」が滞っている方
- 「水」が過剰な方
それぞれ適切なケア方法が異なります。専門家の診断を受けることで、あなたの体質に最適な施術を受けることができるのです。
季節先取りケアのススメ
東洋医学の知恵として、「未病先防(みびょうせんぼう)」という考え方があります。これは「病気になる前に予防する」という意味です。
季節の変わり目の不調を防ぐには、次の季節に向けて2〜3週間前から体を準備することが効果的です!
例えば、夏の終わりから秋に向けては:
- 夏の間に冷やした胃腸を徐々に温める食材を増やす
- 朝晩の気温差に備えて、自律神経を調整するツボ刺激を始める
- 乾燥に備えて、保湿や水分摂取を意識的に増やす
こうした「先取りケア」は、季節の変わり目の不調を未然に防ぐ効果的な方法なのです。
まとめ:季節に左右されない体質を目指して
季節の変わり目の不調は、東洋医学の知恵を取り入れることで、大きく改善できます。ポイントをまとめると:
- 「気・血・水」のバランスを整える
- 季節ごとの特性を理解し、適切なセルフケアを行う
- 予防的なケアを心がけ、季節の変化を先取りする
- 必要に応じて専門家のケアを受ける
日々の小さな習慣の積み重ねが、季節に左右されない強い体質づくりにつながります。
季節の変わり目の不調に悩まされているなら、一度、東洋医学の専門家による体質チェックを受けてみませんか?扶桑町のはりきゅうサロンharuyuiでは、あなたの体質を丁寧に見極め、季節の変化に負けない身体づくりをサポートしています。
初回トライアルでは、普段の生活習慣や症状を詳しくお聞きした上で、あなたに合った施術プランをご提案。季節の変わり目ごとに体調を崩す悩みから解放されるきっかけになるかもしれません。